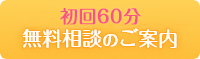遺留分について
遺留分とは、民法において、法定相続人に定められている遺産を相続できる最低限の割合のことをいいます。被相続人の遺言書において遺留分を侵害されていた場合、侵害された者は家庭裁判所に申し立てを行い、遺留分の請求をすることが出来ます。遺産分割協議で相続する割合が決まった場合には、遺留分の請求はできません。
遺留分の権利者について
被相続人の法定相続人(兄妹姉妹を除く)
- 被相続人の配偶者
- 子(子がいない場合は孫)
- 直系卑属である両親(両親がいない場合は祖父母)
上記の者は被相続人の遺言書によって遺留分を侵害された場合、遺留分の請求を行う事が可能となりますが、相続廃除や相続欠格者とされた者には遺留分の権利がない場合もあります。
遺留分の割合
- 配偶者・・・法定相続分の1/2
- 子供・・・法定相続分の1/2
- 両親・・・法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)
遺留分の算出方法
例【夫婦と子供2人の4人家族:夫が死亡】
<夫が知人に全財産を渡すという旨の遺言書を残していた>
⇒法定相続人である配偶者の妻と子は最低限相続できる権利があるので、遺留分を請求することが出来ます。
夫の遺産が預貯金5000万円、債務が800万円
【遺留分の計算式】
| 遺留分の算定の基礎となる財産 | 5000万円-800万円=4200万円 |
|---|---|
| 妻と子供二人合計の遺留分 | 4200万円×1/2 (遺留分の割合)=2100万円 |
| 妻の遺留分 | 2100万円×1/2(法定相続分)=1025万円 |
| 子供(一人分)の遺留分 | 2100万円×1/2(法定相続分)×1/2(子2名)=525万円 |
上記計算式から、妻は1025万円、子供は525万円を最低限相続できる権利があることがわかります。遺言書によってこれを下回っていた場合、遺留分の侵害が認められます。
相続の基礎知識の関連項目
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(土日祝も営業)
みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。