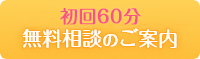改製原戸籍について
改正原戸籍とは
相続手続きにおいて戸籍は非常に大事な書類となります。まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集します。その際に改製原戸籍(「かいせいげんこせき」または「かいせいはらこせき」)という戸籍法が改正される前の様式で記載された戸籍を目にされることがあるかと思います。
また、戸籍をデータ化する際に元となった紙ベースの戸籍も「改製原戸籍」と呼ばれており、法改正での「改製原戸籍」と区別するために「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼ぶこともあります。
戸籍の歴史
明治31年式戸籍
民法において「家制度」が制定されました。戸主に強い権限を持たせ、戸主とその傍系にあたる者までを一つの戸籍に記載した、当時の家制度を反映させた戸籍です。
大正4年式戸籍
戸主以外の家族について詳細に記載し、戸主との関係性が記載されるようになりました。現在残っている大正4年式戸籍は除籍簿、または改製原戸籍になります。
昭和23年式戸籍
それまでの家制度が廃止され、「家」単位で作成されていた戸籍に対して、「家族」単位に変更になり「戸主」が廃止され「筆頭者」となりました。現在の戸籍制度です。
平成6年式戸籍
従来の紙媒体に代わって、コンピュータで管理され、横書きA4サイズの書式に統一するようになり、戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「個人事項証明書」という正式名称がつきました。
相続の基礎知識の関連項目
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(土日祝も営業)
みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。